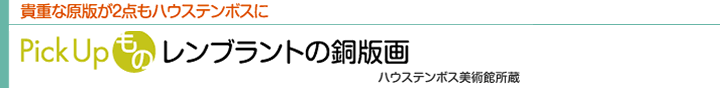17世紀オランダ絵画の巨匠レンブラント。油彩のイメージが強いのですが、実は銅版画でも大きな足跡を残しています。ただ、その原版が確認されているのは世界で80数点。そのうちの2点がなんとハウステンボスにあります。
エッチングの表現広げる功績

2009年2月、石川県金沢市からひとりの女性がハウステンボス美術館を訪れました。金沢美術工芸大学美術工芸学部の保井亜弓准教授。専門は西洋美術史ですが、文部科学省の補助金を得てレンブラントの銅版画を国内外にわたり調査しているスペシャリストです。
そんな人物がなぜ、長崎のハウステンボス美術館まで足を運んできたのでしょうか。

レンブラントはご存じのように17世紀オランダが生んだ絵画の巨匠。《夜警》や《テュルプ博士の解剖学講義》などの油彩で知られ、生涯に600点ほどの油絵を描きました。
その印象が強いからか、ファンの間ではおなじみでも一般の人にあまり親しみがないのが銅版画。実は300点を越す作品があり、銅版画の技法のひとつ、エッチングで大きな功績を残す版画家でもあったのです。

ただ、その原版がすべてどこかで保管されているかというとそうではなく、現在確認されているのは世界でわずか80数点のみ。そのうちの2点《ヤン・アセレインの肖像》と《門づけをする楽士たち》が日本にあるのですが、その所蔵者がなんとハウステンボス美術館なのです。
版画には大きく分けて、銅版画、木版画、リトグラフ、シルクスクリーンがあります。銅版画は銅版に刻まれた線にインクを流し込み、それを紙に写し取るのですが、刻む技法にはエッチング、エングレービング、ドライポイント、アクアチントなどがあります。
レンブラントが得意としたエッチングとは銅版一面を膜でコーティングしたあと、鉄筆で絵を描き、酸に浸して腐食させる方法。技術的にはそう高度なものではありませんが、彼は腐食させる時間やインクのふき取りを調節することによって微妙な濃淡やより繊細に質感を出すことに成功し、表現の幅を一気に広げました。
死後に刷られたものが多数

そもそも、版画が登場したのは15世紀のグーテンベルグによる印刷技術の発明がきっかけです。この印刷という技は「絵画や書物は1点もの」という概念を複製するという概念に変え、芸術や学問を広く大衆へと開放した、いわば情報革命というべきものでした。
そこから版画という分野も生まれたのですが、当時の画家にとって歓迎すべき技術でもありました。というのも、絵画は注文によるものがほとんどで、画家の収入は不安定。そこへ手軽な芸術作品として版画が多くの人々に親しまれるようになり、版画制作が安定した現金収入源となったからです。
レンブラントの画家としての出発点にも版画がありました。デビューしたばかりですから注文もなく現実的な事情からなのでしょうが、彼がすごいのはエッチングを発展させたばかりか、探究心を刷りの紙にも向かわせ、当時出島からもたらされたばかりの和紙を西洋で初めて使ったということです。

けれど、こうした情熱も版画特有の二面性の前に皮肉な結果をもたらすことになりました。二面性とは大量に刷れる反面、版さえあれば誰でも刷れるということ。残念なことに現在、残っている版画の多くがレンブラントの死後に刷られた粗雑なものとわかったのです。
もともと、銅版自体は100枚刷った程度で傷むもの。それを承知で大量に刷られた形跡が認められ、さらに惜しいのは役目を終えた原版は版主が売り払い、あげくに溶かされたとも考えられています。80数点しか見つかっていない理由は、そこにもあるようです。

だから原版はとても貴重なもの。オランダの美術史家たちによって結成され、世界中に存在しているレンブラント作品の調査・判定を行っているレンブラント・リサーチ・プロジェクトも原版を大掛かりに調査し、少しでも多くと、行方を追い続けています。
ハウステンボス美術館は“だまし絵”で知られるエッシャーの作品500点と日本での著作使用権をもちますが、レンブラントの銅版画はそれと並ぶ大きな宝。銅版に刻まれた繊細な線を眺めていると、鉄筆を振るうレンブラントの息づかいも聞こえてくるようで心がときめきます。そして、あらためてその素晴らしさに感動を覚えるのです。